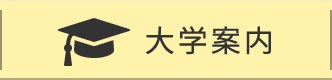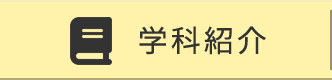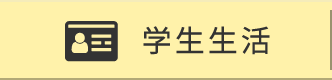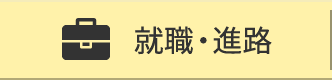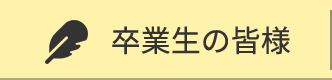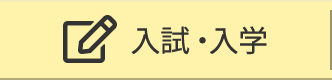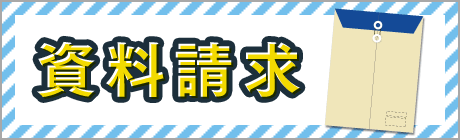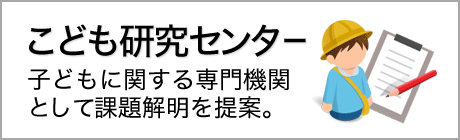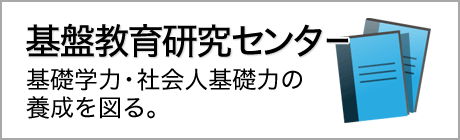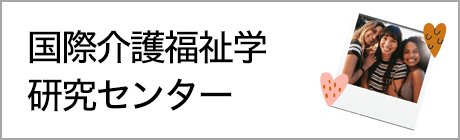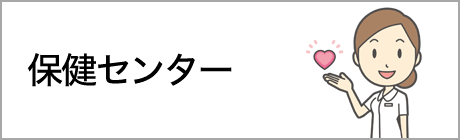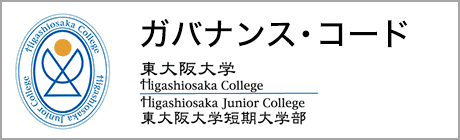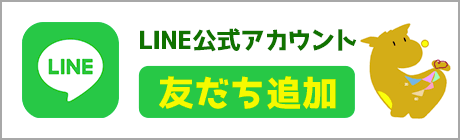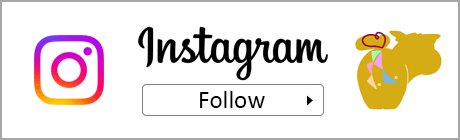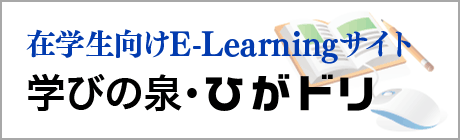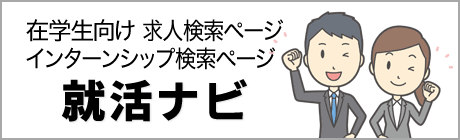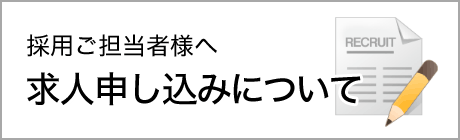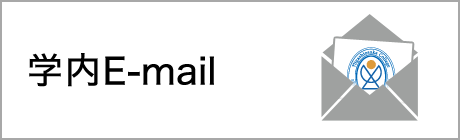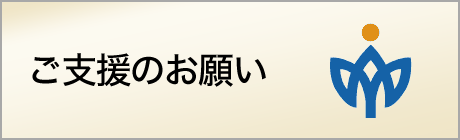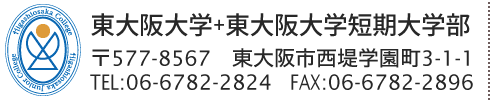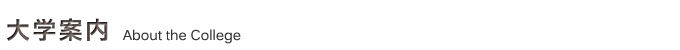
山田 克宏 プロフィール

准教授 [ 修士(社会福祉学)]
山田 克宏 Yamada Katsuhiro
主な担当科目
介護保険制度と介護に関する諸制度, 社会福祉
専門分野
地域福祉, 保育ソーシャルワーク, 社会福祉教育, 精神保健福祉
著書
- 『相談援助演習』第3版・第4版, 共著, 弘文堂, 2018・2020.
- 『ソ―シャルワーク演習(共通)』共著, 弘文堂, 2024.
学術論文
- 「高齢者ケアにおけるリスクマネジメントとソーシャルワークの視点:『当事者』主体から捉えた『ヒヤリ・ハット』」単著, 鹿児島国際大学大学院論集, 第7集, 2015.
- 「人・社会・生活関連科目群の構造化」共著, 日本社会福祉教育学会会誌, 第12号, 2015.
- 「実習におけるF-SOAIP(生活支援記録法)による記録を通じた認識変化の一考察」単著, 敬心・研究ジャーナル, 第5巻, 第2号, 2021.
- 「特別養護老人ホームにおける看取りケア:対人援助職の支援上の価値判断の異同」単著, 秋田看護福祉大学研究所所報, 第17号, 2022.
- 「ICTを活用したソーシャルワークの演習教育の現状と課題:オンライン授業における評価・負担感・満足度から捉える演習教育のあり方」単著, 日本社会福祉教育学会会誌, NO29・NO30合併号, 2024.
- 「『子ども分野』での支援者の記録における必要要素:家族支援を包含した記録の一考察」単著, 東大阪大学・東大阪大学短期大学部研究教育研究紀要, 第22号, 2024.
研究発表
- 「『当事者』主体におけるリスクマネジメント:『ヒヤリ・ハット』を活用したリスク認識の合意について」単独, 日本社会福祉学会, 2015.
- 「事前指定書の意義:クライエントと家族の意見の相違との関係からの一考察」単独, 日本社会福祉学会, 2020.
- 「『社会的ひきこもり』・『ひきこもり』支援:社会・家族との関係から捉えた一考察」単独, 日本社会福祉学会, 2021.
- 「人口減少地域におけるひきこもり支援『効果モデル』開発に向けて:秋田県藤里町における『地域トータルケア・包括的支援』の取組から学ぶ支援モデルの構築」単独, 日本ソーシャルワーク学会, 2023.
社会的活動
- 2024年 大阪社会福祉士会基礎研修Ⅱ 実践評価・実践研究系科目Ⅰ 招聘講師
- 2024年 大阪社会福祉士会中河内支部 研修講師「ひきこもり支援」
- 2023年~ 東大阪市介護認定審査会委員
- 2023年~ 大阪社会福祉士会 中河内支部 支部役員
- 2022年~2024年 大阪社会福祉士会近畿ブロック大会運営委員
- 2022年 仙台市役所健康福祉局保険高齢部 招聘講師
- 2020年~2022年 秋田県社会福祉士会理事
- 2021年~2022年 第三者評価制度 評価委員「秋田県」
- 2011年~ 沖縄大学地域研究所特別研究員
- 2017年~ スーパーバイザー
研究テーマ
- 人口減少地域におけるひきこもり支援の効果的プログラムの開発
- 社会福祉教育におけるICTを活用した効果的な教育方法
- 「こども分野」での支援者の記録における必要要素:リフレクションを促進させる段階的学習プログラムの開発
研究員としての活動、共同研究
- 沖縄大学地域研究所特別研究員として、「ソーシャルエクスクルージョンされづらい地域づくりについて:島嶼地域の取組から」というテーマで研究活動を行う予定としている。
- 「こども分野」での支援者の記録における必要要素:リフレクションを促進させる段階的学習プログラムの開発について共同研究を行うための準備を進めている。
その他
生活支援記録法(F-SOAIP)実践・教育研究所講師
生活支援記録法 F-SOAIP エフソ・アイピー
メッセージ
「福祉とは, 何でしょう。」「介護とは, どのようなことを指すのでしょう。」社会福祉は, 社会的排除されやすいクライエントの支援を行います。しかし, 制度利用やクライエントのニーズ充足だけでは十分ではありません。なぜなら、ひきこもりを続ける人たち, 養護に欠ける子どもたち, ヤングケアラー等の社会的課題は未解決です。クライエントも地域生活をしていますが, 関係の貧困, サポートを頼めない地域環境・社会環境が存在しています。私たち専門職は, サポートをすることを目的化するのではなく、見守り, 声掛けを行い, かかわっていくことが重要です。当事者が専門職に気持ちを発露できるような支援をすることが重要点です。学生の皆さんには、学園訓にある『自他敬愛』の精神に基づき, 多様性を尊重して学生生活を送っていけるようにサポートします。今まで述べてきたことを, 講義, グループワーク, 実習を通じて、共に学びませんか。
一緒に, 明るい未来を創造していきましょう。
自分を信じて💘